goodテーマに参加しよう
気軽に参加できる、集いの場、語らいの場。渋谷に関わる皆さんの書き込みが、渋谷のまちを変えるタネになる!?
まちの未来ついて自由に話し合う場があったとしたらどんなことを話してみたいですか?
まちの未来について話し合う?
まちという存在が当たり前すぎて、普段あまり考えないことかもしれませんが、もっと気軽にまちの未来について自由に話し合えたとしたら、まちはもっと楽しく心地よい場所になるかもしれません。
コロナ禍で社会も変化する中、新年を迎えたこのタイミングで、一度考えてみませんか?
このお題は「自分たちが生きる社会について、安心して話せる学びの場」をコンセプトに活動されているシブヤ大学さんとのコラボ企画として実施いたします。
1/22に開催するオンラインオフラインハイブリッド型セミナー「まちの未来をみんなでつくるには?~バルセロナDecidim活用の取り組みより~」に先駆けて、この場で議論させてください。
いただいたご意見は、セミナーでのディスカッションテーマとしても活用させていただく予定です。
セミナーのご参加者も募集中ですので、そちらも奮ってご参加ください。
ハイブリッド型セミナー概要
日時
1/22(土)18:00-20:30
場所
赤坂BIZタワー23F (東京メトロ千代田線赤坂駅より徒歩5分)
ゲスト
宇野重規先生(政治学者・東京大学社会学研究所教授)
67年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。専門は政治思想史・政治哲学。主な著作に『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社学術文庫、サントリー学芸省)、『保守主義とは何か』(中公新書)、『民主主義とは何か』(講談社現代新書)などがある。
Decidim を運営する一般社団法人コード・フォー・ジャパン東健二郎さま
Decidimを日本で初めて導入した兵庫県加古川市をはじめ各地の自治体や団体と協働した様々な合意形成事例を創出している。2021年4月から滋賀県日野町政策参与も務める。

不適切な内容を報告する
このコンテンツは不適切ですか?
ディベートを終了する
このディベートの要約または結論は何ですか?

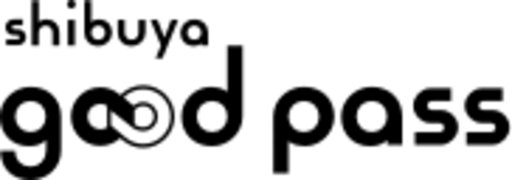


17 件のコメント
コメントを読み込んでいます...
コメントを追加
ログイン または 新規登録 することでコメントできます。
コメントを読み込んでいます...